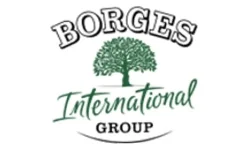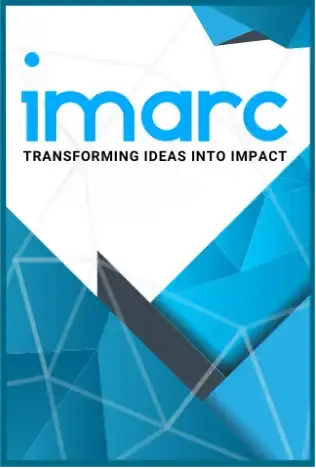
日本の電気バス市場規模、シェア、動向、予測推進タイプ、バッテリータイプ、全長、航続距離、バッテリー容量、地域別、2026-2034年
日本の電気バス市場概要:
日本の電気バス市場規模は、2025年に1,150.4百万米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、同市場が2034年までに3,996.7百万米ドルに達し、2026年~2034年の期間に年平均成長率(CAGR)14.84%で成長すると予測しています。バッテリー技術の進歩、支援的な政策、そしてインクルーシブデザインへの注目が、日本の電動バスへの移行を加速させています。エネルギー効率の向上、コスト競争力、政府補助金、アクセシビリティ機能などが、電動バスの普及を後押しし、車両性能の向上とともに日本の電動バス市場の成長に寄与しています。
|
レポート属性
|
主要統計
|
|---|---|
|
基準年
|
2025
|
|
予想年数
|
2026-2034
|
|
歴史的な年
|
2020-2025
|
| 2025年の市場規模 | 1,150.4 百万米ドル |
| 2034年の市場予測 | 3,996.7 百万米ドル |
| 市場成長率 2026-2034年 | 14.84% |
日本の電気バス市場動向:
バッテリー技術とバス性能の進歩
バッテリー技術と充電インフラの急速な発展により、日本の人口密集都市部における電気バスの実現可能性が高まっている。エネルギー密度、熱安定性、充電効率の向上は、航続距離への不安を和らげ、運行会社にとってはより正確なスケジューリングを可能にしている。重要な例として、東芝は臨港バスおよびドライブエレクトロと協力し、パンタグラフ式超急速充電を採用した日本初の公共電気バスを2024年に導入する。2025年11月までに川崎市で運行を開始する予定で、わずか10分でフル充電が可能な東芝のSCiB電池が搭載された。この進化により、バスの運行フローを中断することなく、短時間の停車中に充電することが可能になり、スペースが限られた都市における基本的な課題に取り組むことができる。このような進歩により、ダウンタイムを最小限に抑え、より定期的な運行が可能になり、交通機関は車両基地を拡張することなく電動車両を拡大することができる。バッテリーの価格が下がり、スマート・エネルギー・システムとの統合が進んだことで、電気バスの費用対効果はディーゼル・オプションに近づきつつあり、運行管理者にとって電気バスへの移行はより魅力的なものとなっている。
政府の脱炭素義務化と補助金支援
カーボン・ニュートラルを達成するという日本の2050年目標は、効果的でスケーラブルな解決策を重視し、電気バスの導入に向けた政策調整と財政支援を促進している。公共交通機関に対する排出削減義務付けは、行政機関によって開始され、新しい電気バスの購入や現在のディーゼル車の改造に対する補助金など、財政的障害を軽減するインセンティブによって支えられている。例えば、住友商事は2024年、東京でディーゼルバスをEVに改造した電気バスを発売し、1台当たりの二酸化炭素(CO₂)排出量を48%削減した。このバスの航続距離は150kmで、EVのコストを下げ、再利用を促進するための幅広い取り組みの一環であった。このイニシアチブは、日本の2050年カーボンニュートラル目標をサポートした。さらに、試験的認可、都市部への配備支援、協調融資を通じたこれらのモデルへの支援は、小規模な事業者でも電化を実現可能にしている。こうした政策と資金調達の複合戦略は、日本の公共交通機関のゼロ・エミッション転換に不可欠である。
公共交通のアクセシビリティと長距離効率に焦点を当てる
日本の電気バス市場の成長は、公共交通機関のアクセシビリティ、効率性、技術的洗練性を高めるという需要に影響されている。ユニヴァーサルデザインへの注目の高まりは、平坦な路面、広い入口、移動が困難な旅行者のための指定エリアなど、アクセシブルな機能を組み込むことをメーカーに促している。こうした設計変更は、特に日本の高齢化人口統計を考慮すると、インクルーシブな都市インフラを奨励する国の政策に支えられている。さらに、乗客の安全性向上とリアルタイムのコネクティビティに対するニーズが、運転支援システム、センサー駆動型アラート、テレマティクス・ソリューションの組み込みを後押ししている。これらの特性は、乗り手の体験を向上させると同時に、車両の監視を簡素化し、事故の可能性を低下させる。アクセシビリティ・ガイドラインと最先端の車両技術が融合することで、排出量を削減するだけでなく、よりスマートで安全かつ包括的な公共交通手段を提供する、最新の電気バスシステムへの移行が加速している。いすゞは2024年、日本初のバッテリー電気自動車(BEV)平床路線バス「エルガEV」を発売した。この次世代バスは、バリアフリー設計、360kmの航続距離、先進の安全性とコネクティビティシステムを特徴としている。
日本の電気バス市場のセグメンテーション:
IMARC Groupは、市場の各セグメントにおける主要動向の分析と、2026-2034年の国・地域レベルでの予測を提供しています。当レポートでは、推進力タイプ、バッテリータイプ、長さ、航続距離、バッテリー容量に基づいて市場を分類しています。
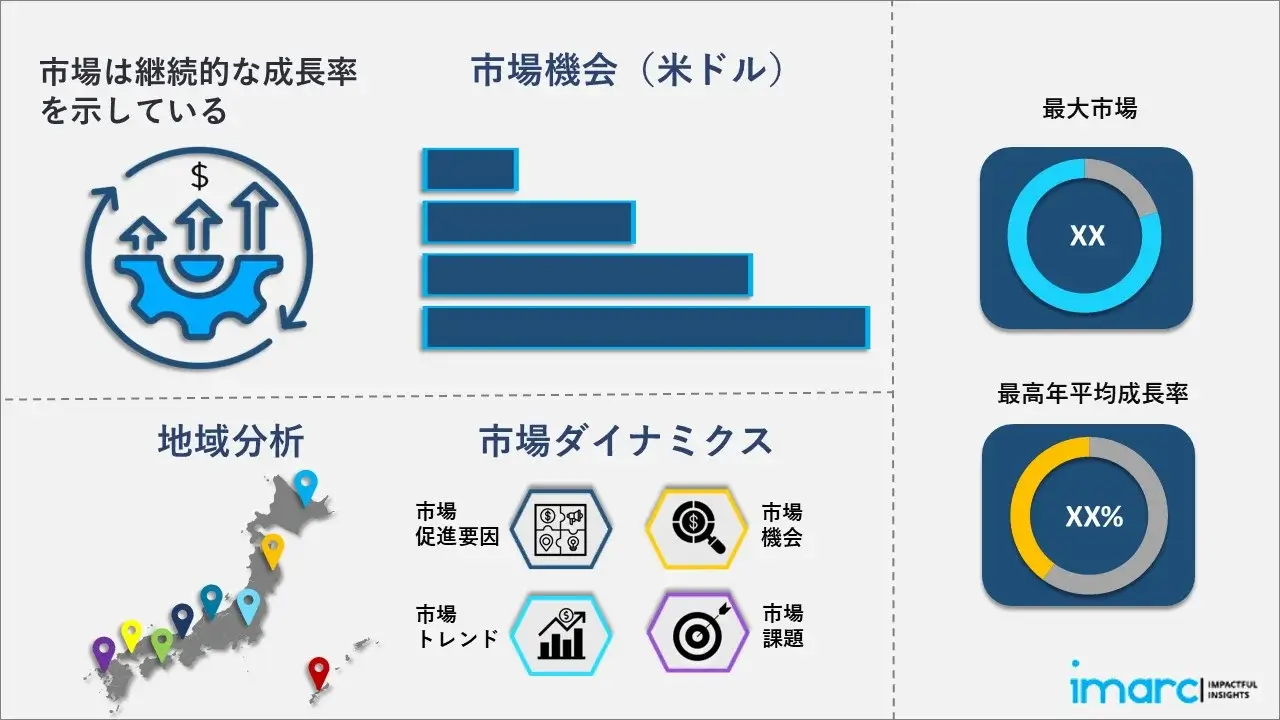
推進タイプの洞察:
- バッテリー電気自動車(BEV)
- 燃料電池電気自動車(FCEV)
- プラグインハイブリッド車(PHEV)
本レポートでは、推進力タイプ別に市場を詳細に分類・分析している。これには、バッテリー電気自動車(BEV)、燃料電池電気自動車(FCEV)、プラグインハイブリッド電気自動車(PHEV)が含まれる。
バッテリータイプの洞察:
- リチウムイオンバッテリー
- ニッケル水素電池(NiMH)
- その他
本レポートでは、電池の種類に基づく市場の詳細な分類と分析も行っている。これには、リチウムイオン電池、ニッケル水素電池(NiMH)、その他が含まれる。
長さの洞察:
- 9メートル未満
- 9~14メートル
- 14メートル以上
長さに基づく市場の詳細な分類と分析も報告書に記載されている。これには9メートル未満、9〜14メートル、14メートル以上が含まれる。
レンジの洞察:
- 200マイル未満
- 200マイル以上
同レポートでは、航続距離に基づく市場の詳細な分類と分析を行っている。これには200マイル未満と200マイル以上が含まれる。
バッテリー容量の洞察:
- 最大400 kWh
- 400kWh以上
本レポートでは、バッテリー容量に基づく市場の詳細な分類と分析も行っている。これには400 kWhまでと400 kW以上が含まれる。
地域の洞察:
- 関東地方
- 関西・近畿地方
- 中部地方
- 九州・沖縄地方
- 東北地方
- 中国地方
- 北海道地方
- 四国地方
また、関東地方、関西・近畿地方、中部地方、九州・沖縄地方、東北地方、中国地方、北海道地方、四国地方といった主要な地域市場についても包括的な分析を行っている。
競争環境:
この市場調査レポートは、競争環境に関する包括的な分析も提供しています。市場構造、主要プレイヤーのポジショニング、トップ勝ち抜き戦略、競合ダッシュボード、企業評価象限などの競合分析がレポート内で取り上げられています。また、すべての主要企業の詳細なプロフィールが提供されています。
日本の電気バス市場ニュース:
- 2025年4月、現代自動車(Hyundai Motor)は屋久島向けにELEC CITY TOWN電気バスを納入し、島のゼロエミッション交通目標を支援しました。これらの中型・ローフロアバスには145kWhバッテリーが搭載されており、屋久島の山岳地形や高湿度気候に合わせて設計されています。この取り組みは、屋久島が目指す2050年までのカーボンニュートラル目標と整合しています。
- 2025年3月、BYD、京阪バス、関西電力は、京都における日本初の全電動バスループ線を発表し、5年間の実証プロジェクトとして開始しました。初期車隊は航続距離150km、充電時間3時間のBYD J6バス4台で構成されています。この取り組みは日本の2050年カーボンニュートラル目標を支援するとともに、京都でのグリーンツーリズム促進にも寄与します。
日本の電気バス市場レポートカバレッジ:
| レポートの特徴 | 詳細 |
|---|---|
| 分析基準年 | 2025 |
| 歴史的時代 | 2020-2025 |
| 予想期間 | 2026-2034 |
| 単位 | 百万ドル |
| レポートの範囲 |
歴史的動向と市場展望、業界の触媒と課題、セグメント別の過去と将来の市場評価:
|
| 推進力タイプ | バッテリー電気自動車(BEV)、燃料電池電気自動車(FCEV)、プラグインハイブリッド電気自動車(PHEV) |
| バッテリーの種類 | リチウムイオン電池、ニッケル水素電池、その他 |
| 対象レングス | 9メートル未満、9~14メートル、14メートル以上 |
| 対象レンジ | 200マイル未満、200マイル以上 |
| 対象バッテリー容量 | 400キロワット時まで、400キロワット時以上 |
| 対象地域 | 関東地方、関西・近畿地方、中部地方、九州・沖縄地方、東北地方、中国地方、北海道地方、四国地方 |
| カスタマイズの範囲 | 10% 無料カスタマイズ |
| 販売後のアナリスト・サポート | 10~12週間 |
| 配信形式 | PDFとExcelをEメールで送信(特別なご要望があれば、編集可能なPPT/Word形式のレポートも提供可能です。) |
本レポートで扱う主な質問:
- 日本の電気バス市場はこれまでどのように推移し、今後どのように推移していくのか?
- 日本の電気バス市場の推進力タイプ別の内訳は?
- 日本の電気バス市場のバッテリータイプ別の内訳は?
- 日本の電気バス市場の長さ別の内訳は?
- 日本の電気バス市場の航続距離別の内訳は?
- 日本の電気バス市場のバッテリー容量別の内訳は?
- 日本の電気バス市場の地域別内訳は?
- 日本の電気バス市場のバリューチェーンにはどのような段階があるのか?
- 日本の電気バス市場における主な推進要因と課題は何か?
- 日本の電気バス市場の構造と主要プレーヤーは?
- 日本の電気バス市場における競争の度合いは?
ステークホルダーにとっての主なメリット:
- IMARC’の産業レポートは、2020年から2034年までの日本の電気バス市場の様々な市場セグメント、過去と現在の市場動向、市場予測、ダイナミクスを包括的に定量分析します。
- この調査レポートは、日本の電気バス市場における市場促進要因、課題、機会に関する最新情報を提供しています。
- ポーターのファイブ・フォース分析は、利害関係者が新規参入の影響、競合関係、供給者パワー、買い手パワー、代替の脅威を評価するのに役立つ。関係者が日本の電気バス業界内の競争レベルとその魅力を分析するのに役立つ。
- 競争環境は、利害関係者が競争環境を理解することを可能にし、市場における主要企業の現在のポジションについての洞察を提供します。
Need more help?
- Speak to our experienced analysts for insights on the current market scenarios.
- Include additional segments and countries to customize the report as per your requirement.
- Gain an unparalleled competitive advantage in your domain by understanding how to utilize the report and positively impacting your operations and revenue.
- For further assistance, please connect with our analysts.
 Request Customization
Request Customization
 Speak to an Analyst
Speak to an Analyst
 Request Brochure
Request Brochure
 Inquire Before Buying
Inquire Before Buying




.webp)




.webp)